
目次
少子高齢化が進行する今の日本で、ケアマネ資格の必要性は年々高まっています。
しかし、SNSなどでは「ケアマネ資格が廃止になる」という噂が広がっているようです。
この記事では、「ケアマネ資格が廃止されるの?」「これからケアマネを目指しても大丈夫?」と不安を感じている方に向けて、ケアマネ資格の廃止が噂される理由とケアマネジャーの必要性、そして資格取得のポイントを紹介します。
ケアマネ資格は廃止されない
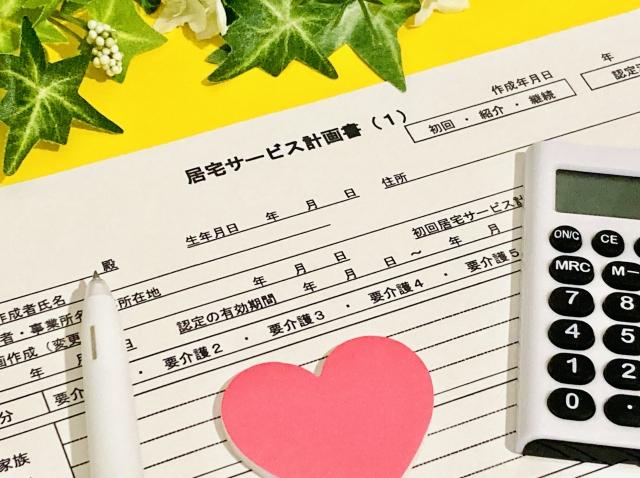
結論からいうと、ケアマネ資格は廃止されません。
2025年現在、廃止に向けた議論は行われておらず、むしろ「対象資格を広げる」「実務経験年数を見直す」といった受験資格の要件緩和の議論がされています。
参考:厚生労働省|ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理 2.人材確保・定着に向けた方策について
なぜケアマネ資格が廃止されるという誤解が生まれたのでしょうか。その理由をみていきましょう。
なぜ「資格が廃止される」と誤解されたのか
誤解を生んだ理由の1つが、ケアマネ試験の受験資格の変更です。
2018年度の制度改正によって、「医療や介護に関する国家資格」「資格に基づいた業務経験」が受験資格に定められました。
これまで認められていた「介護等の業務で実務経験を満たす」というルートは廃止され、制度変更前より受験資格を満たすのは難しくなったのです。
この変更により、2017年に13万1,560人だった受験者数は翌年に4万9,3332人まで減りました(約62%の減少)。合格者数は前年の2万8,233人から4,990人に減りました(約82%の減少)。
参考:厚生労働省|第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
受験者数・合格者数・合格率が減少したことで、ケアマネ資格廃止の噂が生まれたと考えられます。
しかし、受験資格の変更はあくまでケアマネジャーの専門性を高める施策で、資格廃止の動きではありません。
科目免除がなくなったのはどういう意味なのか
ケアマネ廃止の誤解が生まれた原因に「試験科目の免除」も挙げられます。
ケアマネジャー試験には「特定の国家資格を取得していれば一部科目が免除される」という科目免除(解答免除)制度がありました(2015年度に廃止)。
科目免除制度が廃止された2015年度の試験の合格率は15.6%でした。翌年(2016年度)の合格率は13.1%とそれまで20%~40%台で推移していた合格率は10%台にまで落ち込みました。
合格率・合格者数が減少したことからケアマネ廃止の噂につながったと考えられます。
参考:厚生労働省|第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
しかし、科目免除制度の廃止はケアマネジメントの質向上を目的とした変更です。ケアマネ資格の廃止に向けた動きではありません。
科目免除制度が廃止されたあとも、ケアマネ試験は毎年実施されています。
主任ケアマネが必要になったら普通の資格は不要なのか
2018年の介護報酬改定によって、居宅介護支援事業所の管理者に主任ケアマネジャー(以下、主任ケアマネ)を配置することが義務となりました。
2021年4月以降に居宅介護支援事業所を開設する際は、原則として主任ケアマネの配置が必須となりました(2027年3月31日までの猶予期間あり)。
参考:厚生労働省|社会保障審議会 介護給付費分科会 居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分について
参考:厚生労働省|平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(4) ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
主任ケアマネの必要性が増したことも、ケアマネ廃止の誤解を生んだ原因の1つと考えられます。
しかし、主任ケアマネの主な役割は他のケアマネジャーへの助言や指導、そして地域包括支援センターでの地域ケアマネジメントの実践です。
一方、一般のケアマネの主な役割は要支援者・要介護者への適切なケアマネジメントの実践になります。両者の役割は違うのです。
主任ケアマネの必要性が増したからといって、一般のケアマネ資格が不要になるわけではありません。
参考:厚生労働省|主任介護支援専門員研修ガイドライン 6 各科目のガイドライン ①主任介護支援専門員の役割と視点
SNSで上がる「いらない資格」という意見は本当なのか
SNSなどで目にする「ケアマネはいらない資格」「将来性はない」といった投稿は事実なのでしょうか。
厚生労働省がまとめた「介護給付費等実態統計の概況」によると、過去5年間の居宅介護支援の費用額(介護予防サービスは除く)は毎年のように増加しています。
(単位:百万円)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 488,318 | 514,629 | 527,332 | 535,683 | 552,298 |
参考:厚生労働省|介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査):結果の概要
居宅介護支援費とは、介護報酬の一種で、ケアマネジャーが行うケアプランの作成代、サービス事業者との連絡調整サービス費などです。保険者から居宅介護支援サービスを提供した事業所に支払われます。
居宅介護支援費が増加傾向にあることは、それだけ多くのケアマネジャーが要介護者・要支援者に居宅介護支援サービスを提供した証と捉えられるのです。
これからも必要とされるケアマネ資格

第1次ベビーブームで生まれた「団塊の世代」は、2025年に後期高齢者を迎えます。介護を必要とする方が増えれば、国内の介護需要は高まるでしょう。
介護保険制度のマネジメントを担うケアマネジャーは、高齢者福祉の増進に欠かせない仕事といえます。
ケアマネ資格が求められる背景やケアマネ試験制度の概要をみていきましょう。
高齢化社会でますます求められる役割
主要先進国の中で日本の平均寿命は最も長く、健康寿命は男女共に最長です。一方で、出生率は国際的に低く少子化が進行しています。
少子高齢化の進展によって、国内では高齢者世帯と独居高齢者の増加が予測されています。独居高齢者の割合は、2040年に約4割に到達する見込みです。
高齢化社会が続くことで、介護サービスの需要はますます高まるでしょう。ケアマネジャーは支援を必要とする多くの要介護者・要支援者から求められると考えられます。
AI時代でも人の支えが欠かせない仕事
ケアプランの効率的な作成などを目的として、AI(人工知能)をケアマネ業務に導入する動きが出てきています。
たとえば、静岡県では居宅介護支援事業所のケアプラン作成にAIを導入・活用する「ケアマネジメント業務AI導入支援事業」が行われ、業務効率化の実現といった成果を上げています。AIは今後も介護業界に導入されていくでしょう。
参考:静岡県ホームページ|令和6年度ケアマネジメント業務AI導入支援事業の実施成果について
一方で、ケアマネジャーはAIが代替できない業務も担当しています。
それは、相談者の気持ちに寄り添い、話し合いを重ねて適切なサービスを見つけ出すといった「人を直接支える業務」です。
利用者や家族を支えるケアマネジャーは「AIに取られる仕事」ではなく「AIの活用によって介護問題に悩む人を支える仕事」といえるでしょう。
待遇改善が進み働きやすさが向上している
介護業務を兼務する施設ケアマネは「介護従事者」にあたり、介護職員処遇改善加算の対象です。今後も、処遇改善加算の適用や報酬改定によって待遇向上を期待できるでしょう。
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」をみると、ケアマネジャーの平均基本給額等(※)は29万340円。介護従事者の中で2番目に高い数値です。
※基本給(月額)+手当(毎月決まって支払われる通勤手当や扶養手当、超過労働給与等は含まれない)
| 職種 | 平均基本給等 |
| 看護職員 | 29万590円 |
| 介護支援専門員 | 29万340円 |
| 生活相談員・支援相談員 | 27万7,800円 |
| 介護職員 | 25万3,810円 |
参考:厚生労働省|令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要
入所者のケアマネジメントまで担当できる施設ケアマネの需要は高く、資格取得によってより現場で重宝される存在になるでしょう。
合格率の上昇で目指しやすくなっている
ケアマネ試験の受験者数は毎年5万人を超えており、合格率は上昇傾向にあります。
第25回から第27回のケアマネ試験の合格率は以下のとおりです。
| 第25回(令和4年度) | 第26回(令和5年度) | 第27回(令和6年度) |
| 19.0% | 21.0% | 32.1% |
参考:厚生労働省|第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について
さらに、有識者による「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、人材確保・定着に向けて新規ケアマネを増やす議論が行われています。議論されている項目は以下のとおりです。
- ・受験要件に新たな資格の追加
・実務経験年数の見直し
・魅力発信などの取り組みの促進 - 参考:厚生労働省|ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理概要②
国がケアマネ人口を増やそうとしている今こそ、ケアマネ試験の学習を始める絶好の機会です。
主任ケアマネへの道がキャリアを広げる
ケアマネジャーからのステップアップに、主任ケアマネ資格の取得が挙げられます。
主任ケアマネは、居宅介護支援事業所の管理者の設置要件を満たす資格です。
主任ケアマネを取得することで、事業所の新規開設を検討する会社や法人から重宝されるでしょう。
資格手当や業務手当の付与といった好待遇も期待できます。
将来の選択肢を増やしたい方は、ケアマネ資格の取得後にケアマネのキャリアを積み、主任ケアマネの取得を検討してみましょう。
ケアマネージャーの資格を安心して目指すための準備

はじめてケアマネジャーを目指す方なら「何から始めたらいいの?」と迷うかもしれません。仕事が忙しい方なら「限られた時間を上手に活用して資格を取得したい」と思うでしょう。
ここでは、安心してケアマネジャーを目指すための準備のポイントを紹介します。
まずは最新の制度を正しく知ろう
まずは最新の介護保険制度を正しく把握しましょう。
介護保険制度は、社会情勢や介護サービスの需要の変化などに合わせて、およそ3年ごとに改正が行われてきました。
制度改正の内容を知ることは、ケアマネ試験の合格につながります。身に付けた知識は、現場で働く際に役立つはずです。
なお、試験勉強の際は、噂や不確かな情報を避けて信頼できる情報源から学びましょう。確かな情報源から学ぶことで、将来に役立つ知識を得られます。
たとえば、インターネットから情報を得たいときは以下のWebサイトが参考になります。
- ・厚生労働省のホームページ
・独立行政法人や公益財団法人など公益性の高い法人が運営しているWebサイト
・専門家が監修している記事(民間企業が運営するWebサイト)
-
効率よく学ぶなら専門カリキュラムを使おう
- ケアマネ試験の学習を効率よく進めたいなら、教育機関が提供する専門カリキュラムを活用しましょう。
教育機関の専門カリキュラムでは、制度改正や最新の出題傾向が反映された教材を使用しています。
仕事や家事などで忙しい受講生も、無理なく学習効率と合格可能性を高められるのです。
さらに、講師の特別講義やサポートを受けることで、孤独感の解消やモチベーションの維持・向上効果を期待できます。
一度の試験で合格したい方は、専門カリキュラムを検討してみましょう。
資料請求で学習の流れをイメージしよう
未来ケアカレッジでは、経験豊富な講師陣が、最新の試験傾向を反映した質の高い講義を提供しています。
そして、自分に合った勉強スタイルを選びたい方のために、「通学コース」「WEBコース」「公開模試コース」の3コースを用意しています。通学・WEBコースのセット受講も可能です。さらに、対象講座により、条件を満たした方はキャッシュバック制度も利用できます。
各コースの特徴や受講料などの詳細を知りたい方は、ぜひ資料請求から詳しい情報をご確認ください。
ケアマネ試験の勉強を安心して始めるコツは、事前に学習の全体像を把握すること。やるべきことをあらかじめ確認して、ゴール(試験合格)までの道筋を具体的に描くことから始めてみましょう。
まとめ

2025年時点で、ケアマネジャー資格が廃止される予定はありません。
要介護者や要支援者が、適切な介護サービスを利用できるように支援するケアマネジャーは将来性の高い仕事です。
ケアマネ資格を取得するには、はじめにケアマネ試験に合格し、続く介護支援専門員研修を修了する必要があります。
ケアマネ試験は、出題範囲が広く専門知識を問われる試験です。効率的に合格を目指すなら、専門の教育機関を利用してはいかがでしょうか。
未来ケアカレッジでは、ケアマネを目指す受講生の皆さん一人ひとりの学習を、経験豊富な講師陣と独自のカリキュラムで応援します。






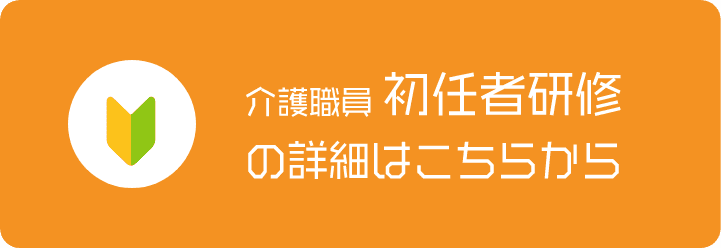
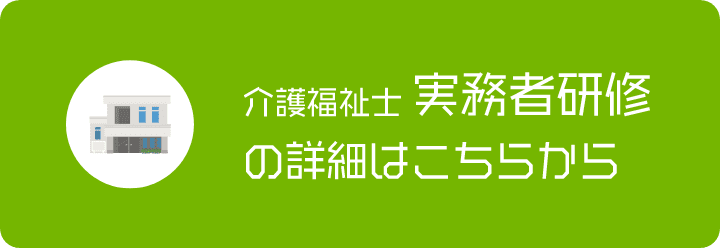



 コラム一覧にもどる
コラム一覧にもどる








